※本記事はプロモーションを含みます。
「申し送りが怖い…」
私もまったく同じでした。
はじめまして。元病棟ナースのぴすです。
私も新人時代は、申し送りが怖くて毎回お腹が痛くなるくらい緊張していました。
申し送りの時間が近づくと、手汗はびっしょり。
「伝え漏れがあったらどうしよう」「先輩に何か言われたら…」って、不安でいっぱい。
頭の中では何度も練習したのに、いざ話すと何を言いたいのか分からなくなって、
帰り道で落ち込む日々。
でも今ではあの頃の自分に、
「怖くて当たり前だよ。少しずつで大丈夫」って声をかけてあげたい。
この記事では、申し送りが怖かった私がどうやって少しずつ“自信”をつけていったのかを、お話しします。
少しでもあなたの気持ちが軽くなりますように。
看護師の申し送りが怖い…そう感じる理由

申し送りが怖い理由は「準備不足」だけじゃない
「申し送りが怖い」――
そう感じてしまうのは、「慣れていないから」「準備不足だから」と言われがちです。
でも、実際はそれだけじゃないんですよね。
これって、看護師なら誰もが一度は感じることだと思います。
とくに新人看護師のうちは、「どの情報が大切か」なんてまだわかりませんし。
申し送りって、ただ事実を伝えるだけじゃなくて、
「次に引き継ぐ人がどう動けばいいか」、「これを知っておけば安心だよね」といった、
相手への思いやりも必要になってきます。
だからこそ、現場経験が浅いと、
“何が正解か分からない”こと自体が、すごく怖く感じてしまうのは当然なんです。
次の人は私の申し送りで動く。その責任がプレッシャーだった
新人のころは、とにかく申し送りの時間が近づくのが怖くて仕方ありませんでした。
引き継ぎの担当者がナースステーションに入ってくるだけで、
「ああ、もうすぐ申し送りの時間だ…」と、そわそわして落ち着かなくなる。
次勤務者にとって、私の申し送りが“ほぼ唯一の情報源”。
私が言わなければ、その情報は伝わらない。
私が伝え忘れたら、そのまま次の勤務に受け継がれない。
それが、ずっと怖かったんです。
“自分の言葉が次の現場を動かす”――そう思った瞬間、
その責任の重さに押しつぶされそうになりました。
メモを準備していても、いざ話すと頭の中は真っ白。
伝え終えたあとに、「ああ、こう言えばよかった…」と後悔して、毎回ひとり反省会でした。
さらに、横で先輩が聞いているプレッシャーも強くて、
「それだけ?」、「で?」なんて返された日は、自信がどんどん削られていきました。
今思えば、それだけ一生懸命だったんですよね。
でも当時は、自分を責めることしかできなくて
「なんで私はうまくできないんだろう」と、落ち込んでばかりいました。
看護師の申し送りでよくある失敗と対策

よくある申し送りの失敗例
新人のころにありがちな申し送りのミスは、実は誰にでも起こり得ることです。
特に多いのは、こんなパターン👇
でもこれって、「慣れていないからミスする」というよりも、
“そもそもどう伝えればいいのか”をきちんと教わる機会がないからこそ起きてしまうんですよね。
看護師の申し送りが怖くなくなる工夫
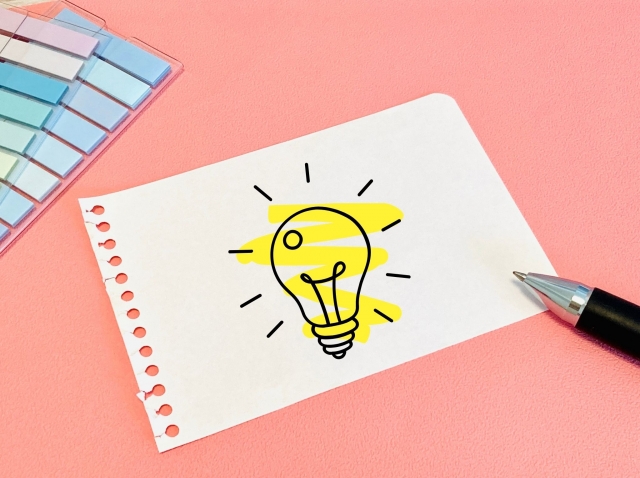
すべて伝えるのをやめた
申し送りがうまくできるようになったきっかけは、
「完璧に伝えなきゃと思うのをやめた」ことでした。
「あれも言わないと」「これも忘れちゃいけない」と考えすぎて、
結局、頭が真っ白になってしまう――そんなことがよくあったんです。
でも、申し送りに対する苦手意識が少しずつなくなってきた今だからこそ言えるのですが、
先輩たちは、ある程度は電子カルテから必要な情報を拾ってくれるんですよね。
それに気づいてからは、
「最悪、これだけ伝えればOK」という自分なりの軸を持って、情報を取捨選択するようになりました。
もちろん、申し送りの形式やカルテの使い方は病院によってさまざま。
なので、まずは自分の職場のルールを最優先にするのが大前提です。
パターンごとに話す順番を決める
もうひとつ、私がすごく助けられたのが、
「患者さんのパターンによって、話す順番をざっくり決めておく」という工夫でした。
「こういうときは、この順番で話そう」とあらかじめ決めておくだけで、
いざというときも落ち着いて話せるようになったんです。
たとえば、こんな感じ👇
🔸新規入院の患者さんなら
→ 基礎情報、入院までの経緯、現在の症状、特記事項・注意点を簡単に。
🔸すでに入院している患者さんなら
→ 状態に変化があったか・なかったかを伝えて → 特記事項(注意してほしいことなど)
🔸急変があった場合
→ 経緯、対応、その後の状態までを、できるだけ詳細に。
最初から完璧に話そうとするよりも、
「この順番で話す」と決めておくだけで、気持ちがグッとラクになります。
そして私がやっていたのは、
「申し送りが上手な先輩の話す順番やパターンを観察して、真似する」ことでした。
「この人の申し送り、聞きやすいな」と思ったら、
話す流れや言い回しをそっとメモして、自分の中に少しずつ取り入れていったんです。
+αの情報や気配りは、ある程度慣れてきてからで大丈夫。
まずは“自分が伝えられること”を、落ち着いて伝えられるようになればそれでOKです。
まとめ|看護師の申し送りが怖いあなたへ伝えたいこと

先輩の申し送りって、とにかく聞きやすくて、
それでいて+αの情報までさりげなく入っていて、本当にすごいなって思いますよね。
でも、最初から同じように話そうとしなくても大丈夫。
「こう話せば正解」みたいな型があるように思いがちですが、実はそうじゃありません。
いちばん大切なのは、
“重要な情報を、相手にしっかり伝えること”。
上手に話すことでも、かっこよくまとめることでもなくて、
次に引き継ぐ人が、患者さんの状態を理解して動けること。
それが、申し送りの目的です。
それさえ意識していれば、
言い方がちょっと違っても、順番が少し前後しても大丈夫。
現場に立つうちに、あなたなりの伝え方が、きっと見つかります🌿
💡あわせて読みたい
▶ 新人看護師が「辞めたい」と思ったら読む記事|限界がくる前に
「今の働き方、ほんとにこのままでいいのかな…」そんな気持ちがあるなら、ぜひこちらも読んでみてくださいね。



コメント